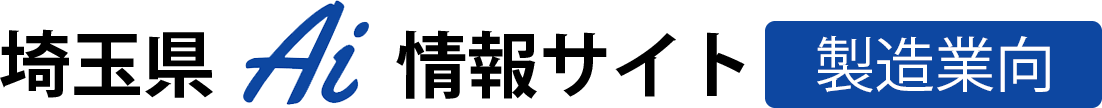はじめに|“AI導入”が空回りする本当の理由
「AIを導入したけれど、現場ではまったく使われていないんです」
──これは、私たちが中小企業の現場でよく耳にする声です。
帳票の自動作成ツール、異常検知のAI、会話型インターフェースなど、確かに「便利そう」なツールは導入された。けれど実際には、現場の社員が使わず、画面だけがホコリをかぶっている。そんな“AI導入の空回り”は、決して珍しい話ではありません。
では、なぜこうした事態が起こるのでしょうか?
DXは「経営の言葉」、EXは「現場の感情」
ここで大切なのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「EX(Employee Experience:従業員体験)」という2つの視点です。
多くの企業では、経営者が「DXを進めよう」と旗を振ります。もちろん、それは正しい方向です。しかし、現場にとってはどうでしょうか?「デジタルで変革を」と言われても、「また難しいことが始まった」「現場が混乱するだけでは?」という感情が先に立ちがちです。
つまり、DXは“経営側の言葉”であり、現場の心を動かす言葉ではないのです。
それに対してEXは、“現場の感情”に寄り添う発想です。「面倒な作業が減った」「自分の仕事がラクになった」「これは助かる」──そうしたポジティブな体験こそが、AI活用の第一歩になるのです。
今こそ、「使いたくなるAI」から始めよう
AI導入で最初に目指すべきは、「使えるAI」ではありません。「使いたくなるAI」です。
どれだけ高機能であっても、現場が“使おう”と思わなければ意味がありません。逆に、少しの機能でも「助かる」「便利」と思える体験があれば、社員は自発的に動き始めます。
このコラムでは、そうした“EX発想”によるAI導入の考え方と、中小企業でも実践できる導入ステップ、社員が動き出す現場の事例を紹介していきます。
「AIで業務改革をしたい」──もしあなたがそう考えるなら、まず見るべきは、社員の目線と体験です。DXの前に、EXありき。これが、現場で成果を出すAI活用の本当のスタートラインなのです。
第1章|「使えない」ではなく「使いたくない」──現場の本音に目を向ける

なぜAIは“現場に響かない”のか?
AI導入において、最も多く聞かれる現場の声は次のようなものです。
「難しそうだから手を出していない」
「忙しくて試している暇がない」
「正直、なくても仕事は回る」
これらの言葉を聞くと、「やっぱり現場はITリテラシーが低い」と思ってしまうかもしれません。しかし、そうではありません。本質はもっとシンプルです──「現場に響いていない」のです。
AIがどれほど優れた仕組みでも、“誰の役に立つのかが見えない”限り、人は動きません。
ましてや、現場の業務は日々ギリギリのリソースで回っています。「新しいツールを使う」という行為自体が、現場にとっては“リスク”なのです。
「便利そう」だけで動かない理由
経営陣やシステム部門がよく使う言葉があります。「これ、便利そうだよね」「工数削減になるから入れよう」
しかし、“便利そう”と“便利”はまったく違います。
導入担当者にとっての“便利”は、機能や性能の話。でも、現場にとっての“便利”は、「明日からラクになるか?」「面倒が減るか?」という体験の話です。
たとえば、報告書を自動で作成するAIを導入したとしましょう。
一見便利に見えますが、
・入力が面倒
・結局あとで手直しが必要
・操作方法が直感的でないという要素があると、「あのAI、なんか使いにくいよね」という評価に変わります。
つまり、“使える”のに、“使いたくない”のです。
現場の声を拾った企業は強い
一方、現場の声に耳を傾け、「誰の、どんな困りごとを、どうラクにするか」を起点にした企業は、AI導入の成功率が圧倒的に高い傾向にあります。
たとえば、
・朝礼で紙のチェックリストを書いていた現場に、スマホで使える入力アプリ+自動集計AIを導入した
・設備点検のベテラン社員が口頭で教えていた内容を、音声入力+ChatGPTでマニュアル化した
こうした取り組みは、“AIを入れる”というよりも、“現場の面倒をちょっとAIで減らした”という感覚に近いものです。それゆえ、現場も拒否感なく、むしろ「助かる」「もっとこうしてほしい」とフィードバックが生まれる。これこそが、成功するAI活用のスタートです。
「使えないAI」ではなく、「使いたくないAI」になっていないか?
それを見極める鍵は、現場の言葉にあります。
第2章|EX(Employee Experience)とは何か?──AI導入に必要な“共感の視点”

EX=従業員体験がなぜカギになるのか
AIを導入しただけでは現場は変わりません。
本当に必要なのは、「AIを使う側の体験」=EX(Employee Experience)の視点です。
EXとは、社員が日々の業務の中で感じる“体験価値”のことです。「この仕事、意味あるな」「この仕組み、助かるな」と感じてもらえるかどうか。そこが、AI導入が成功するか失敗するかの分かれ道になります。
なぜなら、AIは現場の道具であり、感情のないシステムではなく感情をもった人間が使う道具だからです。
導入側が「工数削減になる」「データ化できる」と喜んでも、現場が「面倒が増えた」「監視されてるみたい」と感じてしまえば、AIは“押しつけられたツール”にしかなりません。
現場での「やりがい・納得・安心感」
EXを高めるために重要なのは、以下の3つの感情です。
1. やりがい
「この仕事は自分にとって価値がある」と思える状態。AIが単純作業を減らすことで、より“人間らしい仕事”に集中できるようになると、やりがいは高まります。
2. 納得
「なぜこのツールを使うのか」が腑に落ちている状態。納得感のない導入は、「なんで今これやるの?」という不信感を生みます。
3. 安心感
「失敗しても大丈夫」「ちゃんとサポートがある」と感じられる状態。
AIがミスしたときのフォロー体制や、操作ミスしても戻せる仕組みなどがあると、安心してチャレンジできます。
これらの感情が揃って初めて、社員が自発的に動き出す組織になります。
ユーザーとしての社員を“顧客”と捉える発想
ここで視点を変えてみましょう。
社員=ユーザーであると同時に“顧客”でもある。
これは、AIを導入・推進する立場の人にとって、非常に重要なマインドセットです。
たとえば、スマホアプリやWebサービスを開発する際、ユーザーの声を徹底的に拾い、使いやすさを磨きます。同じように、AIを現場に導入するなら、社員の使い心地・使いたい理由・不満点を“顧客の声”として受け取る必要があるのです。
・「どこが使いにくい?」
・「どんな場面なら助かる?」
・「何が不安?」
こうした声に耳を傾け、フィードバックを反映していくことこそが、EXを高める第一歩です。
AI導入の成否は、EXをどれだけ設計できるかにかかっています。“人間中心”で設計されたAI導入こそが、現場に定着し、結果としてDXを加速させるのです。
第3章|社員が動き出す!“EX発想”によるAI導入5ステップ
EX(従業員体験)の視点が重要であることは分かった。では、実際にどうすれば「現場が動き出す」AI導入ができるのでしょうか?
ここでは、中小企業の製造現場でもすぐに実践できる、“EX発想”による5つの導入ステップをご紹介します。
ステップ①|現場の困りごとを“定量化”する
最初のステップは、「なんとなくの不満」を数値で捉え直すことです。
例:
「作業にムダが多い」→ 1日に○分の手書き作業が発生
「情報がバラバラ」→ 品質データを探すのに○分かかる
感覚的な不満では、AI導入の目的がぼやけてしまいます。一方、時間・件数・工数などで“見える化”できれば、「この部分をAIで改善したい」という共通認識が生まれ、現場の納得感が大きく変わります。
ステップ②|ツール選定を「一緒に」行う
AIツールの選定は、つい管理部門や経営層だけで進めがちです。しかし、現場に使ってもらうことがゴールである以上、“使う人”を最初から巻き込むことが欠かせません。
操作画面の見やすさはどうか?
導入後の業務フローはどう変わるか?
どんな不安があるか?
こうした対話を通じて選ばれたツールは、“現場が納得して選んだ”という実感が伴うため、導入後の定着率が格段に高まります。
ステップ③|初期運用は“簡単で効果が見える”ものにする
AIの導入初期は、「このツール、使ってみて良かった」という“小さな成功体験”を現場に届けることが大切です。
そのためには、
操作が簡単
導入の手間が少ない
数日で“効果が見える”
この3拍子が揃ったテーマから始めるのが鉄則です。
たとえば、「日報作成をChatGPTで自動化」「紙帳票をスマホで記録し、AIで集計」といった取り組みは、数日で「ラクになった」と実感しやすく、社員の抵抗感を大きく減らします。
ステップ④|現場リーダーを巻き込む
現場が本当に動くためには、キーパーソンとなる“現場リーダー”の協力が不可欠です。
このリーダーは、必ずしも肩書きが“係長”や“課長”である必要はありません。むしろ、現場の信頼を集めているベテラン社員や、普段から周囲に教える立場の人のほうが影響力は大きいものです。
このリーダーに、
まず使ってもらう
改善点をフィードバックしてもらう
周囲に使い方を広げてもらう
といった役割を担ってもらうことで、“現場発”でのAI活用文化が自然に根づいていきます。
ステップ⑤|成功体験を全社で共有する
最後のステップは、成功体験を“個人の満足”で終わらせず、組織の財産として共有することです。
Before/Afterの比較データ
現場社員のコメント
活用方法のショート動画
などを通じて、「AIでこんなにラクになった!」という事例を社内に広げることで、他部署や他工場にも展開の波が生まれます。
社員の中に「今度は自分もやってみたい」という声が出てくれば、AI導入は一過性の“プロジェクト”から、持続的な“文化”へと変化します。
現場が動き出す鍵は、「技術」ではなく「体験」にあります。そして、その体験を生み出すためには、“経営目線”ではなく“現場目線”の導入ステップが欠かせません。
第4章|中小企業の“動いた現場”に学ぶ──社員が主役になったAI活用事例
「ウチの現場でもAIって使えるのだろうか?」
そんな疑問に応えるのが、すでに“動き出した”中小企業の現場事例です。ここでは、社員が主役となってAIを活用し始めた3つの事例をご紹介します。
いずれも高額なシステム導入ではなく、「目の前の困りごと」にAIを当てはめたシンプルな取り組みばかりです。
1|工場内のマニュアル自動作成(ChatGPT × 現場)
ある金属加工業の企業では、「人によって作業手順がバラバラ」という悩みが長年続いていました。ベテランは自分のやり方で進め、新人にはなかなかノウハウが伝わらない。しかも、手順書を作る余裕がないのが現場の実情でした。
そこで導入したのが、ChatGPTを使った「マニュアル自動作成支援」です。
手順を口頭で説明しながらスマホで音声入力すれば、ChatGPTがそれを文章に変換し、見出し付きのマニュアルに自動整形してくれます。
たとえば──
作業名(例:ボール盤での穴あけ)
手順(ステップ1〜3)
注意点・コツ(過去の失敗談も含む)
といった形式に自動でまとめられるのです。
これにより、現場の人が“話すだけ”でノウハウが可視化されるようになり、新人教育や業務標準化が一気に進みました。
2|品質記録の自動整理 → 現場の手間が1/3に
ある食品加工業では、毎日の「品質記録」が現場の大きな負担になっていました。紙の記録を記入 → 担当者が手でExcel入力 → 上司に提出、という手順が定着しており、記録業務だけで1日1人・1時間以上かかっていたのです。
そこで採用されたのが、スマホ入力フォーム+AI整理ツールの組み合わせです。
現場では、スマホで記録をタップ入力するだけ。AIが自動的に以下を行います。
項目の抜け漏れチェック
異常値のハイライト
時系列での一覧化(グラフも自動生成)
その結果、記録→整理→確認の手間が従来の1/3に。なにより、現場からは「作業に集中できるようになった」「記録が楽になった」と喜びの声が上がりました。
3|ベテランの知恵をAIに“残す”取り組み
どの中小企業にも共通する課題──それがベテラン社員の「経験の継承」です。
ある精密部品メーカーでは、30年以上の経験を持つ職人がそろそろ引退を見据えているにも関わらず、「ノウハウが頭の中にある」「伝え方が分からない」という状態が続いていました。
そこで行われたのが、AIによる“知恵の棚卸し”プロジェクトです。
社員がベテランに「どうやって判断してるの?」とインタビュー
回答をテキストにし、ChatGPTに入力
ChatGPTがそれを「判断基準」「チェックポイント」として文章化
完成したのは、「AIがまとめたベテランの知恵ノート」でした。これを元に社内マニュアルや教育資料が再構成され、技術継承の見える化が大きく前進したのです。
「AIを使う」のではなく、「社員が“動いた”AI活用」
これらの事例に共通しているのは、「社員が自ら使いたいと思える形」でAIが活用されているという点です。
技術ではなく、困りごとから始めたこと
押しつけではなく、一緒に作ったこと
革命ではなく、日々の改善から始めたこと
そうした小さなアプローチが、結果的に現場を動かし、企業を変えていきます。
第5章|「現場が変わる」と会社も変わる──EX視点がもたらす好循環
EX → 自発性 → 継続活用 → DXへ
多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を掲げています。しかし、実際には「ツールは入ったけど活用されていない」「現場との温度差が埋まらない」という声が絶えません。
その最大の原因は、順番を間違えていることにあります。
DXの出発点を「経営の視点」ではなく「現場の体験=EX」に置くと、導入の意味も、社員の動き方もガラリと変わります。
具体的には、以下のような流れが生まれます。
EX(良い従業員体験)→ 社員の自発性が芽生える→ AIが“使われる”ようになる(継続活用)→ 仕事の質やプロセスが変わる(DX)
AIという道具が単なる“機能”ではなく、“現場に喜ばれる体験”として浸透すると、社員自身が「もっとこう使えないか?」と考えるようになります。
その発想と試行錯誤こそが、企業の真の変革(DX)を引き起こす原動力になるのです。
小さな成功が“次の挑戦”を生む
重要なのは、大きな改革をいきなり狙うことではありません。
日報作成が5分早くなった
マニュアル作りがラクになった
社員が「これいいですね」と言った
そうした小さな成功体験が、社員の心を動かします。
すると、「じゃあこの作業にもAIを使ってみようか」という次の挑戦が生まれます。さらに、その成功体験が社内に共有されれば、他部署にも自然と広がります。
つまり、“成果→共感→拡散”というポジティブな循環が動き出すのです。
このような循環は、トップダウンでは生まれません。現場に寄り添った導入と、現場から湧き出る意欲によってしか動き出さないのです。
「EX経由のDX」という新しい道筋
これまでのDXは、どちらかといえば“業務効率化”や“IT化”を主語にして語られてきました。しかし、今後の中小企業に必要なのは、「社員が気持ちよく働き続けられる仕組みとしてのDX」です。
そのための入り口が、EX(従業員体験)です。
「社員の不満」から出発する
「ラクになった」という体験を届ける
「もっとやってみたい」という声を引き出す
こうしたアプローチを通じて、経営改革ではなく、“職場改革”から始まるDXが生まれていきます。
私たちはこれを、「EX経由のDX」と呼びたいと思います。
現場を起点に、未来をつくる
AIもDXも、最終的には人の意欲がなければ根付きません。だからこそ、まず動き出すのは「システム」ではなく「社員」であるべきです。
EXを起点にした小さな変化が、現場の空気を変え、やがて会社全体の変革へとつながっていく──それが、無理なく、自然に、そして持続可能なDXのかたちです。
おわりに|“社員の体験”から始めよう
現場から始まる本当のDX
DXとは、単なるIT導入ではありません。それは、働き方や考え方、そして組織の空気が変わることです。
そしてその第一歩は、華やかなシステム導入やトップの宣言ではなく、現場の一人ひとりが「ちょっとラクになった」と感じる日常の変化から始まります。
だからこそ、AI導入において最も大切な問いはこうです。
「この仕組みは、社員の体験をどう変えるか?」
この問いを起点に、AIを“使いたくなる存在”として設計していくこと。それこそが、持続可能で、人に寄り添ったDXの本質です。
変革は、“現場の納得”から始まる。
あなたの会社のDXは、すでに始まっています。それは、新しい道具を入れた瞬間ではなく、社員が「これはいいね」と言った瞬間に、静かに始まるのです。