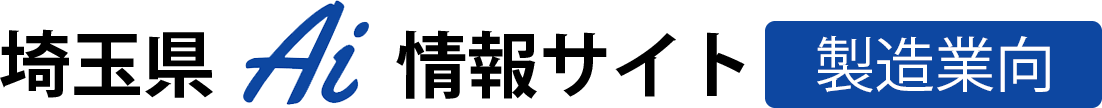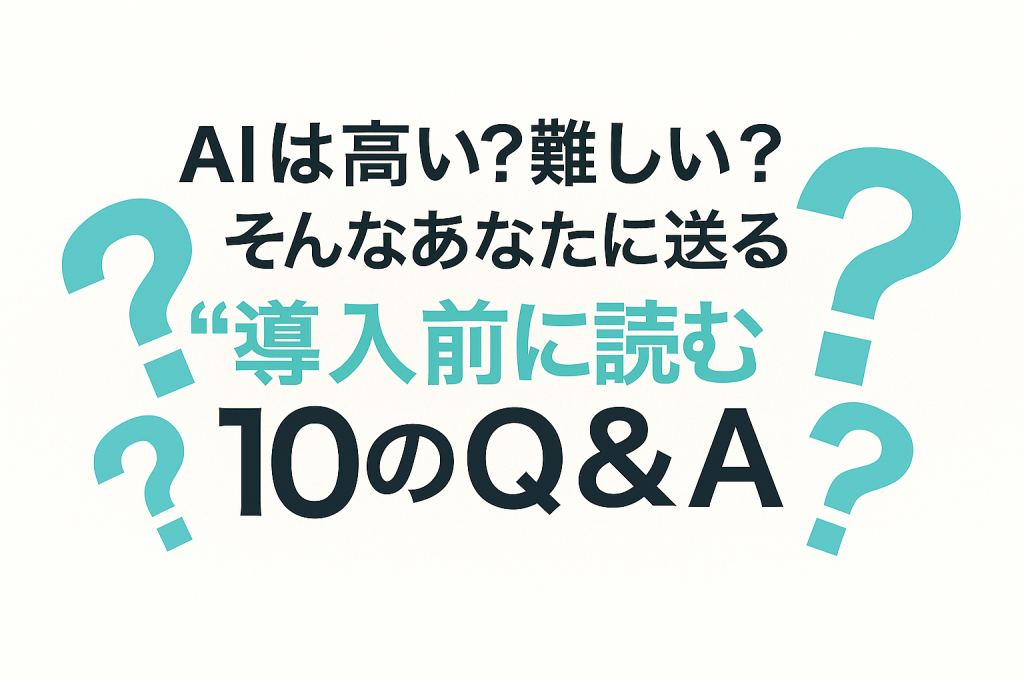
「AIって興味はあるけど、結局よくわからない」
「ウチみたいな小さな工場には関係ないと思ってた」
そんな声を、私たちは日々たくさん伺います。
でも実は、AIは“少人数・アナログ業務が多い”中小製造業こそ相性がいいのです。
難しそうに見えるAIも、今では無料で試せるツールや、助成金と連携した支援制度も整ってきています。
とはいえ…
- 専門知識がないとムリ?
- 費用はどれくらいかかる?
- 誰に相談すればいいの?
そんな疑問があるのも当然のこと。
そこで今回は、中小製造業の現場からよく聞かれる「10のQ&A」をまとめました。読み終わった頃には、きっと「ちょっと相談してみようかな」と思っていただけるはずです。
記事の最後には、埼玉県内の支援先フォームへのリンクも掲載しています。
「何から聞けばいいかわからない方」も、お気軽にどうぞ。
Q:AIって何ができるの?
A:AIは、決して「人間に代わってすべてをこなす魔法のロボット」ではありません。
一言で言えば、「決まったルールに従って判断・予測・生成する賢い補助ツール」です。
たとえば製造業では、次のような活用がすでに始まっています。
・過去の不良データをもとに、異常の予兆を検知する
・ベテラン社員の経験をもとに、作業マニュアルを自動生成する
・工場内の画像や音声を解析し、見えづらい問題を“見える化”する
・取引先とのメール文案や報告書を下書きする(ChatGPTなど)
つまりAIは、「考える」よりも「整理する」「気づく」「繰り返す」が得意。
人手が限られる中小企業こそ、日々の“もったいない作業”を減らすために活用しやすい存在です。
Q:ウチみたいな中小企業でも使える?
A:はい、むしろ中小企業こそAIの恩恵を実感しやすい立場にあります。
AIというと「大企業が使うもの」「ITに強い企業じゃないと難しい」というイメージがあるかもしれません。ですが実際には、日々の業務が属人化していたり、紙やExcelで処理されている現場こそ、AIの小さな導入で大きな効果が出るケースが増えています。
たとえば、
・毎月の報告資料を自動生成
・製造実績の入力ミスを自動チェック
・紙の帳票をOCR+AIでデジタル化
・営業日報を話すだけで自動要約
といった「小さな自動化」でも、月10時間以上の工数削減につながった例もあります。
AIを“特別なもの”と考えるのではなく、「道具のひとつ」として、小さく取り入れてみる。それが、導入成功の近道です。
Q:費用が高そうだけど…?
A:今は“ほとんどコストをかけずに”始められる方法がたくさんあります。
一昔前まで、AIの導入といえば数百万円単位の開発費やシステム構築が必要でした。ですが現在では、以下のように費用を抑えてスタートする選択肢が整っています。
・無料で使える生成AIツール(ChatGPT、Notion AIなど)
・月数千円〜のクラウド型AIサービス
・IT導入補助金や自治体の支援制度を活用した実証導入
・相談無料の公的機関(SAITEC、産業振興公社、DX推進ネットなど)
特に埼玉県では、中小企業のデジタル化を支援する体制が充実しており、「とりあえず話を聞いてみる」だけでも得られる情報は多くあります。
大事なのは、“最初から完璧なAI導入”を目指さないこと。
まずは、自社の課題に合った「小さな一歩」を、無理なく始めることです。
Q:専門知識がないと難しいのでは?
A:専門知識がなくても大丈夫です。最近のAIツールは「誰でも使える」ように進化しています。
たとえばChatGPTのような生成AIは、特別な操作を覚える必要はなく、普段の会話と同じように「これを作って」「これを直して」と話しかけるだけで、文章やアイデアを提示してくれます。
また、今は「ノーコード」と呼ばれる、プログラミング不要のツールも増えており、
Excelの延長のような感覚で、業務の一部を自動化することもできます。
よくある活用例:
・入力した内容から見積書や議事録を自動作成
・よくある質問をAIが代わりに答えるチャット窓口を設置
・写真を撮るだけで在庫カウントや部品の識別
つまり、AIに必要なのは“技術”よりも“使い方の発想”です。
「この作業、毎回やってるけど、誰かに任せられたらな…」
その気づきこそが、AI導入のスタートラインです。
Q:効果はどうやって測るの?
A:工数削減、エラー減少、時間短縮など「数字で可視化」できるKPIを一緒に設計できます。AI導入は感覚よりも、客観的な変化で評価できます。
多くの中小企業で、「AIって本当に効果あるの?」「やってみたけど、成果がよく分からない」という声を聞きます。
その原因の多くは、導入前に“測る基準”を決めていなかったことにあります。
たとえば、以下のような項目は、AIの効果を分かりやすく評価する指標になります。
- 作業時間(1件あたり何分短縮されたか)
- エラー件数(転記ミス、確認漏れなどの削減)
- 担当者の作業負担(業務の自動化・分散)
- 報告や見積の作成時間(何回分を自動化できたか)
AIの導入は「ふんわり便利」ではなく、数字で実感できる“業務改善です。
そのため、支援機関では導入支援とあわせて、KPI(成果指標)の設定や検証サポートも行っています。
「効果が分からなかった」で終わらせないために、最初の設計こそが成功の鍵です。
Q:ウチの業務のどこにAIを使えるか分からない
A:工程表や作業フローを一緒に見ながら「手間が多い」「判断が必要」「ルールがある」部分を洗い出せば、AI導入ポイントが見えてきます。
「AIを使えるところがない」と感じるのは、自然なことです。
でも実際に、社内の業務を棚卸ししてみると、AIが得意とする“隠れたチャンス”が見つかるケースは多くあります。
たとえば、次のようなパターンです:
- 毎月決まったフォーマットで作る書類やレポート
- 人によって対応がバラつく作業(見積、問い合わせ返答など)
- 目視や経験に頼って判断している工程(検品、仕分けなど)
こうした業務には、「繰り返し」「判断」「ルール」というAIが力を発揮しやすい条件がそろっています。
「どこから始めればいいか分からない」ときは、支援機関と一緒に業務フローを見える化することが第一歩になります。
AIの導入は、技術からではなく、「現場の困りごと」から始めるのが成功の鉄則です。
Q:どのAIツールを選べばいいの?
A:ChatGPTやGoogle製ツールなど、目的によって向き不向きがあります。自社の課題に応じた“道具選び”は、支援機関や専門家が伴走可能です。
AIといっても、ひとつの製品ではありません。
用途に応じて、さまざまなツールがあります。
たとえば…
- ChatGPT(OpenAI):文書作成、マニュアル作り、メール文面の下書きなど
- Google Cloud AutoML/Vertex AI:社内データを使った予測・分類モデルの構築
- AI OCR(文字認識)系ツール:紙帳票やFAXデータの自動読み取り・デジタル化
- 画像認識AI:検品や外観判定など、目視作業の支援に
しかし現場では、「いろいろあって選べない」「高機能すぎて使いきれない」といった声もよく聞きます。
そこで大切なのは、“AIを選ぶ”よりも“何を改善したいか”を明確にすることです。
その目的がはっきりすれば、自然と「必要なツール」「不要な機能」が見えてきます。
支援機関や専門家は、こうした目的ベースのツール選定と導入サポートに対応しています。
「迷ったら聞いてみる」で十分です。AI導入は、“相談しながら選ぶ時代”になっています。
Q:失敗したら怖い…
A:小さく始めて、小さく検証。現場の“困りごと”を解決する形でスタートすれば、リスクは限りなく低く抑えられます。
AI導入と聞くと、「万が一うまくいかなかったら…」「投資がムダになるのでは…」と不安になるのは当然です。
でも実際には、AIは一気に大規模導入する必要はありません。
たとえばこんな始め方があります。
- 1人の担当者が、1つの業務にだけ試してみる
- 無料ツールで操作感をつかむ
- 月に1時間だけAIに任せてみる
このように、“トライ&エラーを前提にした設計”であれば、
仮にうまくいかなくても失うものは少なく、学びは確実に残ります。
さらに、支援機関を活用すれば、導入計画の段階でリスクを整理したり、想定効果を事前に検討することも可能です。
大切なのは、「完璧な成果を出す」よりも、「社内にAIを試す文化を育てること」。
AI導入において“失敗しない方法”は、実は「失敗しながら学ぶ」ことなのです。
Q:ウチに合う活用方法が分からない
A:それを一緒に考えるのが“支援機関”の役割です。まずは、気軽にご相談ください。
「AIがすごいのは分かるけど、うちの業種・規模では何に使えるか分からない」
という声は、製造業をはじめとした多くの中小企業から聞こえてきます。
実際、活用方法は企業ごとにまったく違います。
同じ「部品加工業」でも、工程の種類や社内体制、抱える課題が違えば、最適なAIの使い方も変わってきます。
だからこそ、最初のステップは「聞くこと」です。
たとえば…
- 図面管理や工程記録の“手書き”をデジタル化できるか?
- 自社の品質データはAIに使えるのか?
- 工場内のどこにセンサーやカメラを置けばいいのか?
こうした悩みは、自社だけで悩まず、公的支援機関や専門家と一緒に整理することができます。
Q:導入後、社員に使ってもらえるか不安です
A:現場で“便利だった”という小さな成功体験を共有することがポイントです。強制せず「試してみる」文化をつくることで自然に広がります。
AIを導入しても、実際に“使ってくれるかどうか”は別問題。
よくあるのが、「管理者は導入に前向きだったのに、現場では誰も使わない」というケースです。
その原因は、多くの場合“説明不足”と“押しつけ”です。
AIを使うには、ちょっとした学習や慣れが必要です。
そこで最も効果的なのが、「自分たちの仕事が楽になった」というリアルな体験の共有です。
たとえば…
- 「日報が自動でまとまって驚いた」
- 「議事録をAIに任せたらすごく助かった」
- 「確認作業のダブルチェックが減った」
こうした前向きな声を社内で広げていくことで、AIは“面倒な新技術”から“便利な道具”へと認識が変わっていきます。
導入段階では、「全員にやらせる」ではなく「1人がやってみる」で十分です。
まずは使ってもらう。その積み重ねが、自然と社内のAI文化を育てていきます。
終わりに
AI導入は、最初の一歩が一番大変。でもその一歩を、私たちが一緒にサポートします。
下記より、お気軽にお問い合わせください!
- DX推進ネットワークへ相談する
- ものづくり支援(埼玉県産業振興公社)へ相談する
- AI・IoT支援(SAITEC)へ相談する